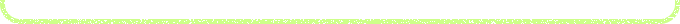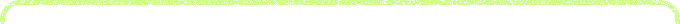
すくすく日記
運動会のあとだって
第41回運動会
10月8日(日)第41回藤田幼稚園運動会が秋晴れのすばらしい天気の中、盛大に開催されました。当初は7日を予定しましたが前日からの雨を考慮し、幼子達の運動会はできるだけ少しでも良い環境で開催してあげたい思いから、親御さん方のご理解のもと前々日からの延期となりました。本当にありがとうございました。
なぜ運動会をするの?…心を強くし、体を丈夫にし、やさいしい気持ちをもち、すべての人にありがとうの思いを伝えるために…と、運動会の練習中つねにその思いを子どもも先生も共有してきました。『愛する人をありがとうの気持ちで喜ばせよう!』と・・・頑張りました。当日の子どもの姿、子ども達の取り組み、子ども達の表現の中にその思いを感じていただけたでしょうか?
幼稚園の生活でいろんな行事があります。私たちは行事を行うことが目的ではありません。子どもの出来栄えや習得度を見世物にする行事ではありません。子ども自ら一生懸命に取り組む、友達のため、お父さんお母さんのため、家族のため、そして自分のために!その意識や思いから自らの心を体をたくましく育んでほしいという願いと祈りで行事を進めています。
その分、私たち大人は自己欲求を自制をし、周りの人たちと協調し共鳴し、子どもの頑張りに寄り添って行くことが大切です。本園の運動会はまさにその集大成ともいえると思います。皆様のあたたかなご理解とご協力で、このすばらしい運動会が41年ものあいだ、問題なく開催し続けられています。この伝統はこれからも次の世代につないでいく大切な宝です。子どもは世界の宝、人類の宝です。この子らの未来が輝き続けますように!!! これからも本当の行事を追求してまいります。保護者の皆様にはまた何かとご協力をお願いする事もありますが、今後ともよろしくお願いします。 運動会お疲れ様でした。ありがとうございました。
スイカたべたぞー!
運動会ごっこ
巨大スイカ
昨日、穴原の小林さん(ミノル工務店)から幼稚園にそれは驚く巨大スイカを頂きました。幼稚園の中庭に置くとどこともなく子どもたちが集まってきました。見たこともない大きさのスイカに大興奮!「見てみて」「すごい」「たべれるのかな」「おいしいかな」「大きいからみんなでたべれるね」・・・・それは多くの感想や言葉が飛び交い興奮の楽しい時間を皆で共有しました。地域の方からの贈り物で子どもたちも楽しい時間を過ごすことができました。また、日頃よりここ大淵地域の人たちの子ども達への愛情に心から感謝しています。家庭・地域・幼稚園(学校)が子どもをまん中にして考える事は何よりも社会の幸福につながると信じています。敬老の日も今週ありました、命をつなぐリレーは私たち人類の尊い営みです。そして、支え合い寄り添い合って生き合うことができる社会をどんなに文化文明が進みデジタル社会になってもその原理原則を忘れてはならないと、巨大スイカを眺めながら思いました。ありがとうございました。
落花生の収穫
今日、落花生の収穫にいきました。サツマイモのつるさしの後、PTA会長さん、農協部農会、農協の職員の方々のお力で、ふれあい畑で落花生を育てていただきました。その収穫に向かいました。年長さんが落花生を枝のまま抜き、そのまま園に運び全園児で落花生を取ります。子どもたちの集中力はそれは頼もしく予定時間より早くそして上手に収穫ができました。農協でその落花生を洗って届けていただきました。取れたての白く輝くきれいな落花生、約9キロを湯で落花生にして、残りは生のままお土産にしました。持ち帰る子どもたちはそれは誇らしい気持ちでしょう。だって自分の手を顔を真っ黒に土にまみれての収穫でしたから、少しですがご家庭で湯でそのおいしさに感動をお願いします。
この落花生は大淵ブランドとして地域の産物として今後おおきく広げていくそうです。地域からおしいい産物が発信されることは私たちにとっても嬉しいことです。みんなで応援していきましょう。この味がふるさとの味になり、子どもたちの感性になり、ふるさとへの愛着になればいいですね。・・・子どもらに伝える大切な思いに・・・
2学期始まりました!
8月31日始業式いよいよ2学期が始まりました。夏休みの経験や体験がこれほどまでも子どもたちをたくましく成長させるのかと?久しぶりに会う子どもたちの姿に感動しています。長い休みで退行現象もみられる事もありますが、それはそれ家庭での暖かな生活に戻りたい思いでしょうから当たり前の事、しかしこれからはそれに代わる幼稚園生活を楽しく有意義な毎日にしていくのが私たちの役割でもあり、子どもたち自身がもつ潜在能力からの心情意欲=パワーで2学期を送って行きます。1日には早々防災訓練、お休みを挟んで運動会の練習も頑張っています。やはり子どもたちはお友達の出会いを待ち遠しくしていたのか、既に毎日を意気揚々と過ごしています。この2学期は1年間で一番長くまた多くの行事もあります。皆さんと共に夏秋冬をまたがるこの時期を精一杯に胸を張り、顔を上げ空を高く仰いで、有意義に過ごして参りましょう。よろしくお願いします。
夏季保育(後期)
遊戯室の屋根
夏季保育
7月31日から夏季保育です。今年の夏は猛暑が続きます。子どもたちの体はまだまだ成長過程です、発汗と水分補給を毎日くり返し、たくましい身体を育んでいきます。しかし、私達人間は如何に楽に心地よく生活できるかをテーマに文明を発展させてきました。しかしそのためのランニングエネルギー、電気やガス、固形燃料など地球の物質を消費して維持しています。また、停電になればそんな文明は一瞬にして使用不可能に陥ります。だからこそ、私達は人間という生物であることを基本にして、文明を発達させ活用することを忘れてはならないと思います。汗して活動し遊び、水を取り、日光で骨を作り、豊かな自然物を頂き、生物力を育んで行くことは様々な環境に適応する力を身につける事になるのですね。子ども時代を如何にすごすか、すごさせたいか、私たちの願いは・・・子どもの未来のために・・・